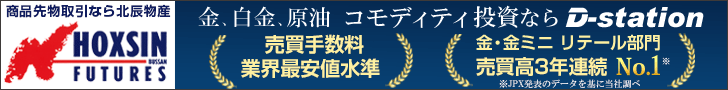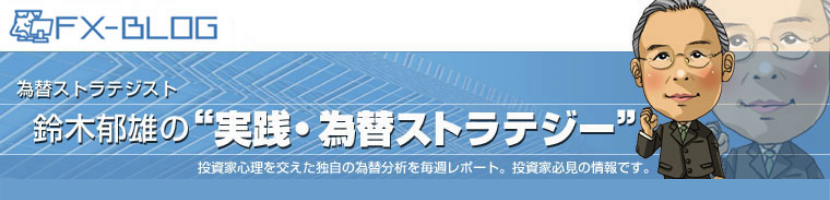安全資産の円高最終局面入り??
市場は全般的に中国経済の減速懸念を背景に、産油国や輸出依存国は厳しい状況に置かれれているが、OPEC総会の進捗状況に不透明感が残る中、原油価格が再び30ドル割れになるなど、依然として、リスク回避的な動きが優先されている。その中、国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事は、今月開催されるG20財務相・中央銀行総裁会議では、各国の政策決定が世界経済に及ぼす影響について集中的に協議する必要があるとの考えを示した上、日米欧の中銀がそれぞれ異なる金融政策に関して、一段と協調する必要がある旨を述べている。ただ、日米欧のそれぞれの政策方針には中国経済を発端としたリスク回避の動きによるところが大きく、協調姿勢を高めるには、とりあえず、為替及び株価の安定化を図ることが先決かもしれない。補足的になるが、中国経済の減速懸念が高まって以来、この3か月間で円は対ドルでは10円程度、そして、欧州通貨やオセアニア通貨に対しても10円以上も円高になっていることを踏まえれば、円高は最終局面を迎えつつあり、当面、ドル円110円前後が下値の目処と言っても何ら不思議ではないのかもしれない。
一方、ドル円はリスク回避を背景に段階的に戻りの鈍さが目立ち始めている。ただ、現状の株価や円高水準では、政府日銀による株価や円高対策への期待感も一部にあり、短期筋としても、ドル円112円前後では実需並びに利益確定買いも散見されるなど、拙速的に円買いを仕掛ける難しさがある。
他方、ユーロドルはマイナス金利拡大を背景に、依然として、上値の重い展開を強いられているが、キャメロン英首相は欧州連合(EU)首脳会議が英国のEU残留に向けた改革案で合意したことを受け、残留の是非を問う国民投票を6月23日に行うと表明している。ただ、メルケル独首相は英離脱問題の協議を再開するが、キャメロン英首相の提案にすべてが合意することは難しいと述べるなど、国民投票結果の行方は予断を許さない状況であり、ユーロ及びポンドがどちらに転ぶかは視界不良の様相を呈している。当面、レンジ幅を1.1050〜1.1250まで拡大し、逆張り待機が賢明であろう。