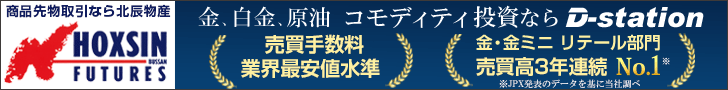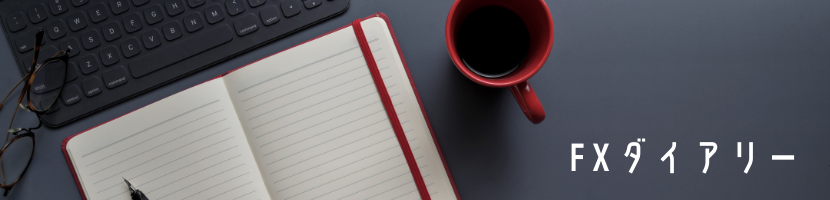IEとEE :カバー取引を観察する視点
■視点
カバー取引の仕組みは、一般にはわかり辛いもので、その分析に当たっては、よくよく真実を見極めながら一つ一つの事実に当たっていかなくてはならない。
現在規制当局が興味をもっているであろうと推測される視点としては、取次ぎ型のカバーモデルとそうでないもの。また、そうでないものの中ではどのようなカバーのロジックを搭載しているか、そして最終的にはその業者がどれくらいの市場リスクを抱えるか、ではないかと思う。信託による分離保管が義務付けられても業者破綻というトラブルはあってはならないものであるという当たり前な前提からくる問題点である。今後このテーマはいろいろな機会や視点で議論されるだろうが、議論する人たちの事実(実態)認識や、互いの視点がずれていたり、使われる用語の定義がまちまちだったりするとまともな結論や評価は出てこない。一例として、私がカバー取引を観察する場合にはめ込む視点を僭越ながら紹介させていただく。
1)ポジションのつかみ方:「グロスヘッジ」か「ネットヘッジ」か
グロスヘッジとは、売りでも買いでもばらばらにきたものは全部ヘッジするモデルである。一方、ネットヘッジは、一定のインターバルや何がしかのロジックを間に入れてその中で客の売りと買いを一定の基準でマリーしながらネット=出っ張ったポジションだけをカバーするモデルである。(ここでのグロスヘッジとネットヘッジは私の造語である。)
2)時間的インターバル
一般にグロスヘッジモデルを採用するとそれはリアルタイムでのヘッジとなることがあたりまえである。逆に言えば、リアルタイムでやるという前提を取るからネッティングする暇がなく、結果グロスヘッジとなる。
ネットヘッジをする場合は必ず時間的な束ね処理(マリー)が必要になるので、リアルタイムでネットヘッジは理論上ない。1秒毎であっても束ねたらリアルタイムとは言わない。
リスク管理上最悪なのは、この時間軸が不定のケースである。ディーラーや会社の恣意的判断によって、場当たり的に、部分的にあるいはすべての出っ張りをヘッジするというものである。経験豊富なディーラーがいるから大丈夫という考えに基づいた安心感だけがよりどころで、リスク管理としては最低であるが、その程度でもびくともしない頑強な財務体質を持っているなら話は別である。
3)アルゴリズム
グロスヘッジには大したアルゴリズムは入ってこない。あるとしたらどのように複数のカバー先に時間的に集中した約定リクエストを分散するかとか、カバー先が拒否した場合の注文の振舞い方をどうするかという約定をいかにスムーズにこなすかという命題に対する対処ばかりである。
一方、ネットヘッジである場合、単純に1分毎もしくは一つの通貨ペアでポジションが100万通貨単位を超えたら速やかにヘッジするというようなロジックから、はてはもっと複雑なアルゴリズムまでいろいろあるだろう。問題はそれらが自社の健全なリスクアペタイトをきちんと理解したうえで作成されているかということと、判断に使われるデータが刻々と変わる状況をきちんとリアルタイムに近い状態で再計算し続けているかという正確性、安定性、再現性の問題がある。あと、時々気になるのが、そのアルゴリズムに顧客ごとにロングショートの情報を取り出してプライスを左右にずらすような機能が入っている場合やいわゆるストップ狩りを行えるようなプライスの反倫理的操作機能である。今の時勢としては訴訟リスクを抱えるモデルである。
4)約定判断:内か外か
自分で約定を判断するか、カバー先に任せるかという意味である。前者をインターナルエグゼキューション(IE)、後者をイクスターナルエグゼキューション(EE)ともいう。後者は証券CFDの用語も転用されDMAとも呼ばれる。DMAはEEの一形態である。
一般にDI業者と呼ばれる業者は前者のIEである。このタイプの場合、そのサービスに約定拒否がない、スプレッドがほとんどの時間帯で固定制、ストップオーダーにスリップがないなどの特徴がでてくる。約定判断を自分がコントロールできるので、要するになんでも可能である。一方、後者EEの場合だと、約定の判断がカバー先任せなので、約定拒否やスリッページが必ずあり、スプレッドは変動制である。インターバンクがそうだから当然それをなぞるのである。
例外として、取引所は取次ぎ型なので、約定はIEなのに、グロスヘッジである。カバー先となる金融機関が、店頭業者に対しては約定判断の権利を渡さないが、取引所に対してだけは、最初から約定を保証するレートだすとこういう例外が生まれる。インターバンクの金融機関はこぞって取引所に特別大サービスをしているわけだが、その分スプレッドは店頭に比べてワイドである。
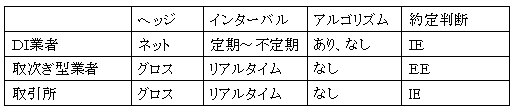
■長所短所
EEというのは、IE業者が手にするこのビジネスのうまみを全部インターバンクに差し上げるモデルでもある。だからIE業者はEE業者よりも約定サービスが良いことがある反面、インターバンクのカバー先から業者へのサービスはEE業者のほうがいい場合がある。
経済合理性から言えばIEのほうがいいことは明らかである。英語でFX業者が Facilitatorと呼ばれる所以でもある。それが認められにくい理由は、3つある。
一つは、そのブラックボックスの中で悪いことが起きているという偏見であり、ときどきその偏見が事実と感じられるようなスキャンダル(以前触れた欧州での訴訟?とかがそれである)が起きること。2つ目は、業者が過度に抱えるかもしれない市場リスクが外から見えないこと、そして3つ目は、業者が巨大になると、ディーリング損益のブレが経営の安定感を阻害することである。これらの問題がない、リスク管理が上手にできる業者であればIEでいいのである。
しかしそれは業者が銀行と対等な規模になることを意味する。そしてそこで集約され合理的にカバーがされることで業者の利益が増加し、その利益の一部がスプレッドの縮小等で投資家に還元されているのであれば、それはFX金融の流通革命のひとつのあらわれといえる。概ね欧州はそういうポリシーを真ん中に置いてやっているように見える。一方米国は、銀行ではない先物業者がリスクをとる必要はないから形式は店頭(OTC)でも実質的には市場リスクを抱える必要のないEE型に特化することをプッシュしているように見える。
最近IEからEEにモデルチェンジをする動きが日本でも出てきている。次回はこの点について触れてみたい。