「為替も“We”の精神で」―尾崎英外 氏[中編]

■為替ヘッジは半年間が限度
窮地を救ってくれたのはバンクオブアメリカ(以下、バンカメ)だった。しかも、バンカメは、億単位でドルを貸してくれた。アメリカでは、米国内の販売店に車を売った代金を回収するネットワークにバンカメを利用していたし、米国トヨタの地元カリフォルニアの銀行だったこともある。この恩を忘れてはならないと、我々は長い間言い合っていたものだ。
73年の308円台から175円台まで円高が進んだドル円は、78年11月のカーターショックを底にして、240円〜60円を行ったり来たりしていた。この時代は、適正な為替レートの方向へ調整されたことと、日本の生産性や品質の向上によって競争力がついたこともあり、為替で、会社の経営に大きな打撃が生じたという記憶はない。それよりもむしろ73年の第1次オイルショックによるガソリン代の高騰のほうが深刻だった。
81年1月に米国トヨタ自動車販売(以下、米国トヨタ)に赴任した。ロサンジェルスの米国トヨタは、総輸入代理店で卸会社。アメリカでの人材が集積していた。この頃、日本は、対米向けの乗用車輸出自主規制を行っていた。

日本の自動車業界自体が自主規制していたので、逆に為替は比較的安定していて、為替レートの変動が自動車ビジネスにとって最も重要な要素にはならなかった。むしろ、売れるのに規制せざるを得ないことのほうが厳しかった。規制対象外だったピックアップトラック(ハイラックス)を一生懸命売っていたことを思い出す。
86年1月に帰国し財務部に戻って、財務企画室長として、そこからまた5〜6年ほど、外国為替にどっぷり漬かることになった。合併以降は、経理部が経理部と財務部に分かれていて、総勢約120人の財務部に外国為替課があり、為替担当者は30人程度いた。
輸出企業は、為替レートの変動に、業績がかなり左右されてしまうので、為替予約(円高による損失を回避するための為替ヘッジ)は非常に重要なことだが、僕は、為替ヘッジの役割は、せいぜい半年から長くても1年程度だと考えていた。一時的な時間稼ぎ、つまり、当期の決算に役立つようなことはできるけれど、それ以上のことはできない。
■企画レートを常に考慮
為替変動に対する本来的な対応は価格改定になる。車だけでなく物の値段というのは、基本的にマーケットの競争関係で決まる。言い換えれば、価格はお客さんが決める。結局、円高分は、中長期的な取り組みにより、原価低減や技術の革新などの企業努力で吸収していくしかない。
しかし、85年9月のプラザ合意以降、円高は急速に進展し、95年に80円を割ってしまったように、この時代の円高は、価格改定ではとても追いつかないほどのスピードになってしまった。
日本の生産性や潜在成長率が高かったにも関わらず、日本の良さであった競争力をはるかに超えた円高になってしまったので、為替変動を企業努力で吸収する時間的な余裕がなくなり、製造業は地方にある工場を海外に移転せざるを得なくなった。最近は、海外から安いモノが輸入されるので、地方の経済はさらに厳しくなってしまっている。地方経済の悪化は日本の為替政策のあり方が引き起こしたことだと思っている。やはり為替調整は真剣に自国の経済や産業の競争力を見ながら規制緩和や構造改革と並行しやっていかなくてはならない。

円高トレンドの中で、僕は、常に車の企画レートというものを考えながらやっていた。製造業は、商社のように、受注イコール採算レートというようにわけにはいかなくて、例えば、新しく自動車の開発を企画する際、海外向けの車に対する為替レート(社内的には企画レートと呼称)の前提を置かなくてはならない。
輸出車の採算ライン(利益の出る水準)は、最初に企画レートを設定しないと算出できない。企画レートは、直近または直近から遡る平均のレートなどがベースとなる。企画レートより円高が進展したら、採算が悪くなり、極端な場合には損を確定するようになってしまうので、こういった場合は予約の比率を落としていた。
逆に、円安に戻っているような状況では、予約を長く取るようにしていたのだが、あまり長く取ってしまっても問題になる。具体的な例として、90年代後半に、日本の不良債権問題等から、146〜147円まで円安に振れたことがある。こうなると、会計上、為替予約による損が大きく発生してしまうので、長期間取り過ぎるのもやはり難しい。
一時、円建ての輸出を拡大した時代もあった。そうすると、日本側の為替リスクはなくなるが、反対にリスクを現地の会社に転嫁することになってしまう。現地の子会社等は独立採算制になっているので、為替の変動を吸収する力はない。この方法はすぐ取り止めとなり、全部外貨建て、それも輸出する先の通貨建てに変更した。為替リスクは、本社がまとめてリスク管理するしか手立てはない。
■自己勘定をほとんどしなかったのは・・・
為替ヘッジ以外の自己勘定部分(資金運用など)においては、為替リスクは絶対とらないという方針だった。なぜかというと、本業が為替リスクに大きく晒されているからだ。
兆円単位もの為替ヘッジを行なわざるを得ないため、多少自己勘定でディーリングしてもあまり意味がない。為替ヘッジによる損得と比べるとディーリングでの損得は知れている。
ただし、予約の比率を決定して、今月中に予約しようとしても、月初が良いのか、月末が良いのか、来週が良いのか、タイミングの判断をする必要がある。需給やチャートなどでその判断しなくてはならないが、ドルの売りばかりやっていて、買いをしていないと相場の感覚が身につかなくなるので、ディーリングは若い部下が小さなポジションで行っていた。

予約が積み上がって、トレンド的に円安に戻っていくと、会社にとっては有難いことではあるが、財務的には含み損のようになってしまうので、持ち値(保有している為替の平均レート)を良くするということで、多少買ったり売ったりするようなことはしていた。
後に、含み損の為替取引を反対売買せずにキャリー・オーバーし、損益を実現しないでいることは不健全だということになり、銀行はいったん反対売買で決済を求めるようになったが、当時はまだフレキシブルで、何回か売り買いをして徐々に持ち値を良くすることができた。
(後編に続く)
*2010年03月15日の取材に基づいて記事を構成
(取材/文:香澄ケイト)
【前編】円高時代に対抗する
【中編】為替リスクと価格設定
【後編】必死でやれば人は育つ
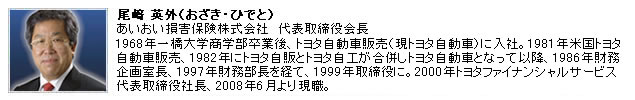
>>「The FxACE(ザ・フェイス)」インタビューラインアップへ




